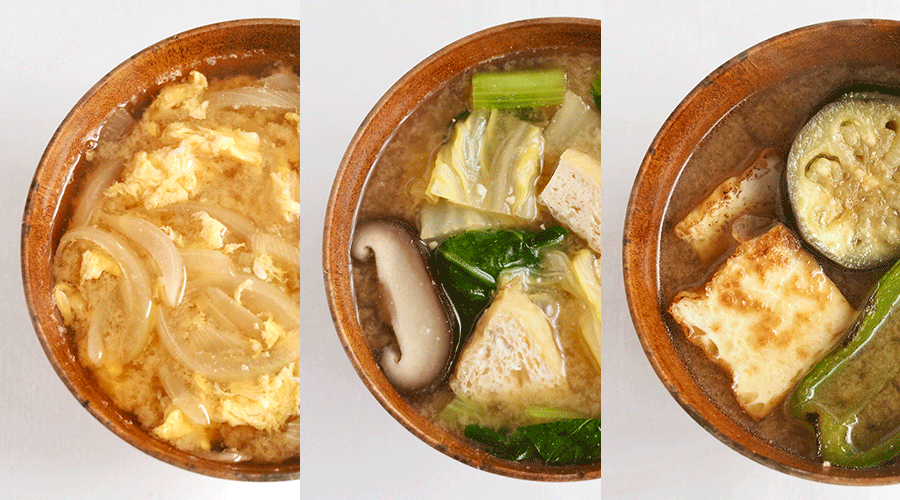東京農業大学・前橋健二先生インタビュー
研究者から見た発酵食品の魅力・すごさとは?科学の目で見た発酵食品【第3回】
前橋健二(東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科教授)

日本の発酵調味料の第一人者で、東京農業大学醸造科学科で教授を務める前橋健二先生に、「発酵」のことを教わる本企画。今回は、先生が専門で研究している発酵調味料「醤油」について詳しく教えていただきます。醤油の歴史から、「醤油」という名前の由来、そして、一般的な醤油から、醤油の原型といわれているたまり醤油、魚で作る「魚醤」、動物の肉で作る「肉醤(ししびしお)」の話に至るまで、醤油の全貌に迫ります!

前橋健二(東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科教授)
日本の調味料研究の第一人者。1969年生まれ、長野県出身。1998年、東京農業大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(農芸化学)。同大学応用生物科学部醸造科学科助手、講師、准教授を経て、2016年より現職。2003年には米国モネル化学感覚研究所にて味覚遺伝子の研究に従事。発酵における微生物と成分変化、発酵調味料、味の解析や味覚のしくみなど、「発酵」と「味」について、多方面から科学的アプローチを続けている。
醤油はいつ生まれた?日本の醤油のルーツとは

――今回は、日本が誇る発酵調味料「醤油」について詳しくお聞きしたいと思います。まず、醤油はいつ頃生まれたものなのですか?
飛鳥時代、701年に定められた大宝律令に「醤」という字が記されています。これは、食料を塩漬けにした保存食「醤(ひしお)」のことで、この頃に中国から日本に渡ってきたものと考えられています。「醤(ひしお)」は固形で、どちらかというと味噌に近い形状の、おかずとして食べるものでした。非常に高級で、限られた層の人たちしか口にできず、庶民にはとても手の届かないものだったようです。この醤をルーツとして、日本の味噌と醤油は生まれたと言われています。
――鎌倉時代に、中国で修行したお坊さんが、日本に帰ってきて醤油を作ったという説もありますが……。
そうですね。そういう説も伝わっています。覚心(かくしん)というお坊さんが中国の宋の径山寺で修行をしたときに、味噌の製法を教わったと。それを日本に持ち帰り、和歌山県にお寺を開き、人々に味噌の作り方を教えたそうです。そして、味噌を作るときに採れる汁が大変美味で、これも調味料に使えるぞということで生まれたのが醤油だと言われています。「醤油」という名前で呼ばれ始めたのは、室町時代。ただ、この頃はまだローカルな調味料で、ほかの土地に広まったのは先のこと。はじめ関西で広まりましたが江戸時代になって江戸でも普及し、江戸時代中期頃になると醤油作りの技術が発達して生産量が増え、関東で工業的に作られるようになったようです。
麹と酵母の力で進化した醤油。さまざまな醤油が生まれました
――「醤油」という字の由来は何なのでしょう?
最初の頃の醤油は、油のようなものが浮かんでいたとも言われていますし、どろっとした油っぽい形状を、もともと一般的に「油」と表していたという説もあります。それが、江戸時代の中期に清酒造りの製法と道具を利用した技術が発達すると、どろっとしていない澄み切った醤油になりました。画期的だったのは、麹と酵母の力を使って、香り高い味に仕上がったことでしょう。そして江戸っ子の濃い味好みに合わせて開発されたのが濃口醤油です。江戸前料理の発達とともに徐々に広まり、全国に行き渡ったのは大正時代のようです。大正時代になるとガラス瓶の大量生産が始まったので、多くの家庭で醤油を取り入れやすくなったんです。濃口醤油のように洗練された香りの醤油は、世界のどこにもないですね。世界一品質の高い醤油だと思います。
――味噌と醤油がメジャーになるまでは、日本にはほかに調味料はあったのですか?
酢がよく使われていました。平安時代の頃の料理の味付けは基本的に塩と酢だけで、刺身も酢につけて食べていたようです。生の魚を酢に漬ける保存料理「なます」は鎌倉時代以前に生まれています。また、出汁と酒を使った調味料も好まれて、鰹節の出汁と梅干しをお酒で煮詰めて作る「煎り酒」という調味料は江戸時代によく使われ、刺身を煎り酒につけて食べるなど、親しまれたようです。その後、醤油が一般的になってからは、煎り酒の出番はぐっと減りました。
――日本には、濃口醤油のほかに、たまり醤油や淡口(うすくち)醤油など、いろいろな醤油があります。これらはどうやって生まれたのですか?
たまり醤油は、日本の醤油の原点だと言われています。昔から現在に至るまで、たまり醤油が作られているのは愛知県と三重県、岐阜県の3県。原料は大豆のみで、大豆で作った麹を塩水に浸して液化させます。鎌倉時代に、覚心が和歌山県に持ち帰ったものは豆味噌の製法でした。その豆味噌の汁で作ったものが日本の最初の醤油だとすると、たまり醤油は、まさにそれと同じと考えていいと思います。たまり醤油のように、どろっとした真っ黒の液体の醤油といえば、西日本で親しまれている再仕込み醤油もそうです。再仕込み醤油の特徴は、何よりも、一度出来上がった醤油で醤油を仕込むという製法。濃口醤油の場合は、大豆と小麦を麹にして、それを塩水に浸して作りますが、再仕込み醤油は塩水の代わりに醤油を使うため、濃厚なうま味を発揮します。別名「刺身醤油」とか「甘露醤油」とも言われています。

――醤油で醤油を仕込む。ユニークな製法ですね。一方で、淡口(うすくち)醤油という、あっさりとした味わいの醤油もあります。いろいろな種類があっておもしろいですね。
淡口醤油は関西地方で発達したもので、色の薄い関西の料理に向くように工夫されたものです。原料は濃口醤油と同じですが、塩を多く加えたり、醸造の期間を短くしたりすることで発酵を抑えるなどの工夫を重ね、着色の促進をゆっくりにしています。また、大豆が黒くならない煮方をするなど、とても繊細な作業が求められます。塩を多めに入れても味が薄い場合は、仕上げに甘酒を加えて甘味を補うことが特徴です。
――淡口醤油よりも色の薄い、白醤油というものもありますよね。
白醤油は非常にローカルな醤油で、江戸時代後期に、愛知県の碧南(へきなん)市で生まれました。主原料は小麦で、大豆はほとんど使わず、2、3ヶ月という短い期間で仕上げます。普通の醤油は半年から1年ほどかけてじっくり熟成させるのですが、白醤油の場合は小麦でんぷんが溶けて自然と垂れてくる汁がもとになっていて、火入れもせず、みりんのような淡い色味に仕上げます。酵母の発酵香もありません。うどんのつゆ、だし巻き卵、茶わん蒸しなど、色をあまりつけたくない料理を作るときに利用しやすいです。考えてみると、愛知県は、濃厚な溜まり醤油とあっさりした白醤油の産地ですね。両極端な個性の醤油が同じ地域から生まれているとは、不思議です(笑)。
大豆や小麦だけではない。肉から作られる醤油も
――日本では、大豆や小麦が原料の「穀醤」が愛されていますが、海外の醤油はどうなのでしょう。アジア圏では、「魚醤油」のナンプラーやニョクマムが有名ですよね。
そうですね。タイではナンプラー、ベトナムではニョクマムと呼ばれていますが、どちらも作り方は同じです。東南アジアからアジア一帯は海に囲まれているのでほぼ魚醤油文化圏で、世界全体で見ても、魚醤油を使っている国は多いです。魚醤油は、もともとは廃棄物利用のような感覚で生まれたもので、あまり上等でない魚を塩漬けにして保存したことが始まりです。魚と塩を3対1もしくは4対1ぐらいの割合で混ぜ合わせて、つぶして放っておくだけ。そして魚が溶けて液体になったものが、魚醤油です。日本でも秋田の「しょっつる」などが伝統的につくられているものの、あまり使われている印象はないのですが、実は全国に魚醤油を作っているところがあります。海外の魚醤油の原料はカタクチイワシが多いのですが、日本の魚醤油はいろいろあります。なかには、鮭、関アジやノドグロなどの名物の魚醤油もありますね。

――魚ではなく、動物の肉から作る「肉醤」というものもあるのですか?
「肉醤」と書いて「ししびしお」とも呼びます。今はあまり見かけませんが、中国には昔、肉を塩漬けにした肉醤がありました。それから、日本では今、鶏肉を塩漬けにして「とりびしお」を作っているところもあります。インターネットで販売していますし、そういった類は地方のお土産屋さんでも見つかると思いますよ。そういえば昔、教え子が自宅で牛肉の醤油を作ったと見せてくれたことがありました。なんだか焼肉に合いそうです。それから、私が在籍している東京農業大学の北海道オホーツクキャンパスでは、オーストラリアの国鳥のエミューの研究を盛んに行っていて、エミューの肉やオイルを使っていろいろな商品を開発しています。そのなかで、エミューの生肉を塩漬けにしたうえで、酵素の力で肉を分解し、加熱も施して「笑友(エミュー)飛翔(ひしお)」という商品を作っていたようです。
――生のお肉を醤油にするとなると少し抵抗を感じましたが、加熱もするのですね。今度、「ししびしお」、トライしてみたいです!
そうですね。ポイントは麹を使うというところです。臭みはまったくなくて、塩味とさっぱりとしたうまみが特徴ですよ。ぜひ、いろいろな醤油を味わって、日本の醤油文化の奥深さに触れてみて下さい。
次回の記事は、発酵食品の味に影響を与えるという「コク味物質」ペプチドについてお伺いしていきます。
※記載内容は、取材対象者及び筆者の個人的見解であり、特定の商品または発酵食品の効果・効用を保証するものではありません。